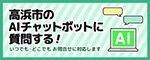本文
令和6年度個人市県民税の定額減税
制度の概要
令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の市県民税において定額減税を実施することが決定されました。
所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm<外部リンク>
定額減税の対象となる方
令和6年度の市県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下)の方が対象となります。
※ただし、以下の場合に該当する方は対象外となります。
・令和6年度個人市県民税が非課税の方
・令和6年度個人市県民税が均等割・森林環境税のみ課税の方
定額減税額
納税義務者本人の定額減税額は、次の金額の合計額です。
ただし、その合計額が個人市県民税の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。
- 納税義務者本人・・・1万円
- 控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する方(納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方)については、令和7年度個人市県民税の所得割額から1万円を控除します。
定額減税の方法
給与所得に係る特別徴収の場合(住民税を給与から差し引いている方)
令和6年6月分は徴収せず、「定額減税「後」の年税額」を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で割った税額を徴収します。
普通徴収の場合(住民税を納付書や口座振替等により納付する方)
「定額減税「前」の年税額」をもとに算出した第1期分(令和6年6月)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月)以降の税額から、順次控除し徴収します。
公的年金等に係る所得に係る特別徴収の場合(2年目以降の方)
「定額減税「前」の年税額」をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除し徴収します。(仮特徴収税額からは控除しません。)
公的年金等に係る所得に係る特別徴収の場合(初年度の方)
令和6年度分の個人市県民税において初めて公的年金等に係る所得から特別徴収される場合は、令和6年6月及び8月は普通徴収の方法による控除を実施し、控除しきれない場合は令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。
注意事項
各制度における算定基礎となる所得割額への影響について
ふるさと納税の特例控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税「前」の額となることから、ふるさと納税の控除上限額が引き下がることはありません。
公的年金等に係る所得に係る令和7年度の仮特別徴収額(令和7年4月分、6月分、8月分)の算定の基礎となる令和6年度の所得割額は、定額減税「前」の額となります。
定額減税をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から 、「 定額減税の関係で還付を受けられるので 」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや 、ATM を操作していただくような連絡をすることはありません 。
不審な電話や SMS 、被害の相談については、 警察相談専用電話(「# 9110 」番)にお電話いただくか、お近くの警察本部又は警察署にお問い合わせください 。
定額減税をかたった不審な電話等にご注意ください [PDFファイル/461KB]
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)