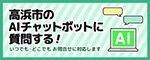本文
後期高齢者医療被保険者証とマイナンバーカードの一体化について
後期高齢者医療被保険者証の廃止について
令和6年12月2日以降、後期高齢者医療被保険者証の新規発行を終了しました。
後期高齢者医療制度に関しては、令和8年7月31日までの暫定的な運用として、令和6年12月2日から令和8年7月31日までの間に、後期高齢者医療に加入された場合や住所、負担割合等に変更があった場合、マイナ保険証の有無にかかわらず、「資格確認書」を発行することとなりました。これに伴う申請は必要ありません。
令和8年8月1日以降については、マイナ保険証の有無によって、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を、お送りする予定です。(令和8年7月中旬ごろ)
後期高齢者医療制度に関しては、令和8年7月31日までの暫定的な運用として、令和6年12月2日から令和8年7月31日までの間に、後期高齢者医療に加入された場合や住所、負担割合等に変更があった場合、マイナ保険証の有無にかかわらず、「資格確認書」を発行することとなりました。これに伴う申請は必要ありません。
令和8年8月1日以降については、マイナ保険証の有無によって、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を、お送りする予定です。(令和8年7月中旬ごろ)
「限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証」について
被保険者証の廃止に伴い、「限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証」についても新規発行を終了しました。
【マイナ保険証をお持ちの場合】
医療機関でマイナ保険証を提示し、情報提供に同意することで、支払いを限度額までにすることができます。申請の必要はありません
【マイナ保険証をお持ちでない場合】
資格確認書に限度額の区分を記載するため、任意記載事項併記申請が必要です。ひと月の医療費が高額になる可能性のある方(入院など)は、お早めに申請をしてください。
【マイナ保険証をお持ちの場合】
医療機関でマイナ保険証を提示し、情報提供に同意することで、支払いを限度額までにすることができます。申請の必要はありません
【マイナ保険証をお持ちでない場合】
資格確認書に限度額の区分を記載するため、任意記載事項併記申請が必要です。ひと月の医療費が高額になる可能性のある方(入院など)は、お早めに申請をしてください。
詳しくは、後期高齢者医療制度の給付をご確認ください。
「資格確認書」について
「資格確認書」とは、マイナ保険証をお持ちでない方が、従来の被保険者証と同じように医療機関を受診できるものです。令和8年7月31日までは、マイナ保険証の有無にかかわらず、資格確認書をお送りします。
「資格情報のお知らせ」について(令和8年8月以降交付予定)
「資格情報のお知らせ」とは、マイナ保険証をお持ちの方が、ご自身の資格情報を把握できるものです。資格情報のお知らせでは、医療機関の受診ができませんので、ご注意ください。
なお、保険証廃止(新規発行の終了)後の対応等については、本ページの更新時点において、愛知県後期高齢者医療広域連合が予定しているものであり、今後の国の動向等により内容が変更になる場合があります。詳しくは、愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
なお、保険証廃止(新規発行の終了)後の対応等については、本ページの更新時点において、愛知県後期高齢者医療広域連合が予定しているものであり、今後の国の動向等により内容が変更になる場合があります。詳しくは、愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
愛知県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>