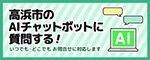本文
国民年金保険料、保険料の免除など
20歳から60歳までの保険料の納付は、大切な義務です。
国民年金保険料は、年金制度を運営するための大切な財源になりますので、期限を守って納めましょう。
保険料額
- 保険料の額は全国一律で、月額17,510円(令和7年度)です。
- 第2号及び第3号被保険者は厚生年金制度が負担しますので個別に納める必要はありません。
付加保険料(月額400円)
- 付加保険料を納めると、老齢基礎年金に加算される形で付加年金が支給されます。付加年金額(年額)は付加保険料納付月数×200円で算出され、物価スライドはありません。
- 第1号被保険者のみが納めることができる保険料です。第2号および第3号被保険者は納めることができません。
- 国民年金基金に加入している方は、付加保険料は納められません。
保険料の納め方
- 国民年金保険料の納め方は、次の方法があります。
・納付書(金融機関の窓口やコンビニエンスストアで納付)
・口座振替
・クレジットカード
・電子納付
・スマ-トフォンアプリを利用した電子(キャッシュレス)決済
・対象の決済アプリはこちら<外部リンク>
・ねんきんネットを活用した「納付書によらない納付」<外部リンク> - 口座振替は毎月の納め忘れがなく確実で便利です。
- 納付書(現金)は、全国の銀行、郵便局、農協、漁協、信用金庫、信用組合、労働金庫で利用できます。利用できるコンビニエンスストアの詳細は、納付書の裏面に記載されています。
- お得な前納制度があります。
保険料の前納制度
| 納付方法 | 種別 | 保険料の額 | 納付月 |
|---|---|---|---|
| 定額保険料(納付書にて納付) | 2年前納 | 409,490円 | 4月 |
| 1年前納 | 206,390円 | 4月 | |
| 半年前納 | 104,210円 | 4月、10月 | |
| 定額保険料(口座振替にて納付) | 2年前納 | 408,150円 | 4月 |
| 1年前納 | 205,720円 | 4月 | |
| 半年前納 | 103,870円 | 4月、10月 |
- 納付書にて2年前納を希望する場合、年金事務所へ申出書の提出が必要になります。
- 前納額が30万円以上の場合、コンビニエンスストアでの納付はできません。
- 詳しくは、刈谷年金事務所国民年金課(Tel:0566-21-2110)へお問い合わせください。
前納を選択した場合の初回の口座振替・クレジットカード納付について
年度の途中からでも口座振替またはクレジットカード納付による前納が可能となります。
- 1年前納または2年前納を選択した方は、初回振替(立替)日に当月分から当年度の3月分(2年前納を選択した場合は翌年度の3月分)までの前納保険料を振替(立替)します。
- 口座振替の6か月前納を選択した方で初回振替日が5月末から9月末となる場合は、9月末までは前月分の保険料を毎月振替し、10月末に9月分の保険料と10月分から当年度の3月分までの前納保険料を振替します。
- クレジットカード納付の6か月前納を選択した方で初回立替日が5月末から9月末となる場合は、9月末までは当月分の保険料を毎月立替し、10月末に10月分から当年度の3月分までの前納保険料を立替します。
- 6か月前納を選択した方で初回振替(立替)日が10月末から3月末となる場合は、初回振替(立替)日に当月分から当年度の3月分までの前納保険料を振替(立替)します。
※月末が土日祝日の場合は翌営業日に振替(立替)になります。
※振替(立替)日については、後日、日本年金機構から開始通知書が郵送されます。
社会保険料控除
- 納めた保険料は、社会保険料として全額所得控除の対象となります。
- これまでに納めた保険料額等のお問い合わせは、刈谷年金事務所へお願いします。
保険料の免除など(保険料を納めることが困難なとき)
法定免除
生活保護法による生活扶助を受けている方、障害年金の1級・2級を受給している方の免除制度です。
免除制度
- 第1号被保険者の方(任意加入者は除く)で、経済的な理由などで保険料を納めることが困難なときは、申請して承認されると保険料の納付が免除される制度があります。
- 前年中の所得額(本人、配偶者、世帯主)などにより審査があり、「全額免除」「半額免除」「4分の3免除」「4分の1免除」または「却下」があります。
- 失業者、被災者を対象とした特例認定区分もあります。
- 免除期間は7月から翌年6月までの間で、申請は原則毎年必要です。
手続きに必要なもの
年金手帳または基礎年金番号通知書、届出人の身分証明(マイナンバ−カ−ド・運転免許証など)、代理人の場合は委任状
未申告、所得状況が確認できない場合は申告等の必要があります。
納付猶予制度
- 50歳未満の方で本人・配偶者の前年の所得が一定額以下の場合に申請して承認されると、保険料の納付が猶予されます。
- 猶予期間は7月から翌年6月までの間で、申請は原則毎年必要です。
手続きに必要なもの
年金手帳または基礎年金番号通知書、届出人の身分証明(マイナンバ−カ−ド・運転免許証など)、代理人の場合は委任状
未申告、所得状況が確認できない場合は申告等の必要があります。
学生納付特例制度
- 学生の方で本人の前年の所得が一定額以下の場合に申請して承認されると、保険料の納付が猶予されます。
- 「学生」とは主に、大学(大学院)、短期大学、高等専門学校、専修学校、および各種学校、その他の教育施設に在学する方をいいます。(昼間部の他に夜間部、定時制課程、通信制課程の学生も含みます)
一部該当しない学校がありますのでお尋ねください。 - 猶予期間は4月から翌年3月までの間で、申請は原則毎年必要です。
手続きに必要なもの
年金手帳または基礎年金番号通知書、在学証明書または学生証(有効期限がわかるもの、コピー可)、届出人の身分証明(マイナンバ−カ−ド・運転免許 証など)、代理人の場合は委任状
未申告、所得状況が確認できない場合は申告等の必要があります。
失業を理由とするとき
失業者特例を利用する場合、上記の各制度に必要な書類とは別に、次のいずれかの書類が必要です。
- 雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証の写し
- 雇用保険資格喪失確認通知書の写し
- 公務員だった方は退職証明(辞令)
- 離職者支援貸付金の貸付けを受けた場合は、貸付決定通知書の写し
免除などは過去2年までさかのぼって申請できます
国民年金保険料の免除などの申請は、過去2年(2年1ヶ月前)までさかのぼって行うことができます。
これらの制度は年金受給権を確保するためにあるものです。将来の老齢基礎年金を受けるときの計算額は、下の表のとおりです。
| 老齢基礎年金を受けるための資格期間には | 受け取る老齢基礎年金への反映 | ||
|---|---|---|---|
| 平成20年度以前の期間 | 平成21年度以降の期間 | ||
| 全額免除 | 受給資格期間に入ります | 年金額に3分の1が反映されます | 年金額に2分の1が反映されます |
| 4分の3免除 4分の1納付 |
保険料の4分の1を納めると受給資格期間に入ります | 年金額に2分の1が反映されます | 年金額に8分の5が反映されます |
| 半額免除 半額納付 |
保険料の半額を納めると受給資格期間に入ります | 年金額に3分の2が反映されます | 年金額に4分の3が反映されます |
| 4分の1免除 4分の3納付 |
保険料の4分の3を納めると受給資格期間に入ります | 年金額に6分の5が反映されます | 年金額に8分の7が反映されます |
| 納付猶予 | 受給資格期間に入ります | 年金額に反映されません | |
| 学生納付特例 | |||
| 未納 | 受給資格期間に入りません | ||
保険料の追納について
保険料免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間については、10年以内であれば保険料を納めることができます。これを追納といいます。
なお、3年度目以降は当時の保険料に加算金がつきます。
追納することにより、老齢基礎年金の年金額に算入されますので、追納されることをおすすめします。追納するためには申し込みが必要です。