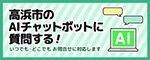本文
一般廃棄物の焼却について
市民の方が、ごみ(一般廃棄物)を焼却する場合には、廃棄物処理法第6条の2第2項の規定に基づく「一般廃棄物処理基準」に従って行うことが必要です。
ダイオキシン類の削減などを目的として、小規模の焼却炉を含めたすべての廃棄物焼却炉の構造に関する基準が、平成14年12月1日から強化されました。
構造基準に適合しない焼却は「焼却禁止」行為となり、罰則が適用される場合があります。
「一般廃棄物処理基準に従った焼却」とは
「焼却設備」(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第3条第1項第2号イに定める「焼却設備」)
次の基準に一つでも合っていない焼却炉は、すべて使用できません。
- 焼却炉の内部と外部が触れることなく、800℃以上で焼却できること
- 焼却に必要な量の空気の通風が行われること
- 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を投入できること
- 焼却室の温度計が設けられていること
- 補助バーナーが設けられていること
焼却方法
- 煙突から焼却灰及び未燃物を飛散させない
焼却量を調整する。(ごみを入れすぎない) - 煙突の先端から火炎または黒煙を出さない
必要な量の空気を入れる。 - 煙突の先端以外から、燃焼ガスを出さない
- 隙間や破損部分がない焼却炉を使用する。
- 焼却中は廃棄物投入口の扉を閉めておく。
※生活環境の保全上いちじるしい支障を生ずる廃プラスチック、廃ビニール、廃タイヤなどの焼却は禁止です。
焼却禁止規定(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第16条の2)
「野焼き」とは、上記以外の「焼却設備」でごみなどを燃やす野外燃焼行為のことで「原則禁止」です。
(例:庭や空き地などで、ごみを燃やす。)
ドラムカンなどの上部を空けたもので、ごみを燃やすことは不適当です。
【野焼き(野外燃焼行為)の例外】として
- 風俗習慣上または宗教上の行為を行うために必要な燃焼
「どんと焼き」などの地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の燃焼 - 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる燃焼
農業者が行う稲わら等の燃焼、林業者の行う伐採した枝などの燃焼 - たき火、その他日常生活を営む上で、通常行われる軽微な燃焼
たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の燃焼
なお、「軽微なもの」とする程度は、社会通念上「たき火」程度
「適正な設備」で「適正な方法」で焼却する必要がありますので、これによらない場合は、市のごみ収集に出してください。(適正な焼却炉を使用する場合でも、近所の方に迷惑をかけないように注意をしてください。)
※住民から煙や臭いによる苦情があるなど、周辺地域の生活環境に与える影響が軽微と認められない焼却は禁止です。